原始仏教と数学
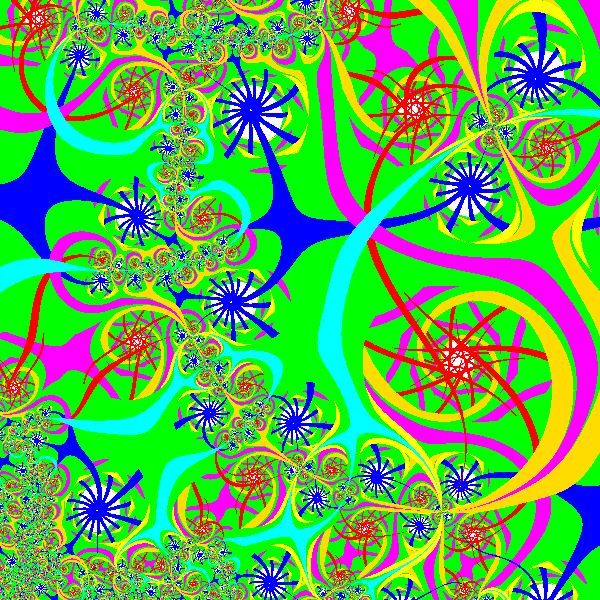
前回の考察は、昨年の3月31日でしたので、ほぼ10ヶ月のお休みということになりました。実はこのHPを立ち上げて、そろそろ10年になり、終わりに近づいた感がありますので、少し充電をする意味で今までの考察を見直していたのです。これからは少しのんびりと、今までの考察の見直しの感想を記述したいと考えています。
今回は、古代インドの思想に影響を受けていると考えられる「原始仏教(初期仏教)」をとりあげ、この考え方が如何に現代の理系の視点、特に数学的センスに適合するかを考察します。
原始仏教とは、仏教の開祖である釈尊(ゴータマ・ブッダ)とその弟子たちの説かれた教えであり、年代としては、釈尊が覚りを得た紀元前420年頃から約200年の期間での仏教をいうといわれています。原始仏教で当時使われていた用語が、後々に体系化され一般的な用語に変わった例は少なくないのですが、ここでは考え方が重要なので、この厳密な区別はせず考察します。
仏教を理解するのに、なぜ数学か
この理由は、「この世の現象は、縁起で生起する」ということが、仏教の基本原則だからです。
すなわち仏教思想も縁起から生起されるのです。「縁起の理」ともいう以上、「因」と「縁」から結果が導かれる筋道が、道理にかなったものでなければならないからです。
このHPを立ち上げて以来、仏教思想を理系の視点で考察を続けてきたのですが、今まで特に矛盾を感じたことはありません。
実は、数学も仏教同様に古代インドで発展したのです。文献(1)によると紀元前800年頃にバラモン教が成立したのですが、バラモン(司祭者)は暦を作り、祭事を司ったのです。祭事とは農業と深い関係があり、一年間の気象を観察して、いつ種をまくか、いつ刈り入れをするかなどを決定し、そのあと収穫祭をいつにするかなどの暦を作ったのです。
つまり、バラモンは天文学の研究者であると共に数学者だったのです。このインドの数学の最盛期は、5 ~ 12 世紀で、この間に負の数や0の発見があるのです。
現在使われている「算用数字」は、インドで創られた0による10進位取り記数法がアラビアを経由してヨーロッパに伝えられたもので、「インド記数法なくして近世西洋数学なく、また近代科学なし」といわれているそうです。
仏教に関しても、古代インドの「業報(ごうほう)」や「輪廻」の思想は、「因果」すなわち現代の「関数」や「因果の連鎖」すなわち「漸化式」の考え方の原点のようなものであり、数学という視点から考察したり、解釈することが可能であろうと考えています。
一般に、時代の変遷にともなって文化も進化し、当然仏教思想も変わり、縁起の考え方も変わる可能性があります。
ただし、古代インドの数学は世界的に有名で、特に代数学が発展したようです。すなわち数値(記号)を用いた定量的で合理的な算法による代数学の考え方は、当時のインドの指導的立場の人の思考に影響を与えたと考えられます。
つまり、仏教思想も縁起の考え方もこのような背景の基で確立していったもので、数学的センスから大きくかけ離れることはないと思うのです。
ただ問題なのは、縁起が日常の言葉で表現されることです。そこで因と縁から結果に至る筋道を、(1)日常の言語で表現する場合と(2)数値で表現する場合について考察します。
(1)因果関係が日常会話によって表現される場合には、因果のつながりはかなり粗いものになり、この世の一切をストーリー(物語)として表現する文系の領域であり、これはいわゆる「状況証拠」のみの推測による因果の関係でも許されるのです。「風が吹けば、桶屋が儲かる」も「あり」なのです。
これに関しては、このHPの見出しのテーマ「涅槃寂静の世界」のシリーズの最初のテーマ「現代は「戯論(けろん)」の時代」でも考察しています。
世の中で生ずる現象のうち、人間の能力の限界で、サイコロを転がしたときのように因と縁を認識できない場合が、きわめて多いのです。この場合人間は「偶然」として取り扱わねばならないのです。
ところが、人間は自己の能力を過信したり、あるいは自己の思惑によって、「偶然」を無視して「必然」として主張する傾向があるのです。
言語で表現する場合、特に「戯論」に近い場合は、因と縁の組み合わせで、結果は如何様にも導くことが可能であり、「縁起」といえども人間の執着や思いこみ、好き嫌いなどの煩悩が大きく影響するのです。
(2)この世の一切の現象を如何に数値による関数として表現できるかの研究そのものが理系の領域です。この場合、筋道はすべて論理的に数式で表現され、人間の思惑のはいる余地は少ないのです。(1)に比較したらとてつもなく厳密なわけで、世の中をより覚めた目で、冷静に見つめることなのです。
つまり、理系は数学という言語を用いて、仏教の基本原則である「この世の一切の現象は縁起で生起する」という考えの基に、学問的に日夜研究しているのです。
以上、数学は、因と縁から論理的な筋道で結果を生起させる唯一の方法なのです。
それにしても、今から2500年も前に、「世の中の一切の現象は変化するものであり、因果関係で表現できる」という考えは、理系の視点としては、驚異的なことなのです。さらに、人間の煩悩を滅却して、物事の因果関係を考えるということは、理系の精神そのものなのです。
原始仏教の基本思想は、現代の「自己制御理論」の原点
ここでは原始仏教の「四つの真理」と「中道」の思想を取り上げます。
「四つの真理」とは、後に体系化され「四諦(したい)」と呼ばれている思想で、(1)「苦」、(2)「集」、(3)「滅」、(4)「道」、の四つで成り立ちます。
(1)「苦」とは、生理的な苦痛や心理的な苦悩のみならず、ここでは「自己の欲するがままにならぬこと」、「我々が自由にならざる境地」を意味します。自由ならざる問題の提示、現代でいう「制御対象」を決定することです。
(2)「集」とは、この自由ならざる対象の変動が生起するさまざまな原因の集まりを調べることです。
(3)「滅」は、消滅の意もありますが、ここでは「抑制する」、「ととのえる」という意味です。すなわち対象の変動の原因が明らかになったところで、この原因を如何に抑制(制御)するかを考えることです。
(4)「道」は、この制御のための実践的な方法(道筋)を提示することです。
以上のように現代でも通用する、問題を解決するための思考の手順であり、制御装置を設計するときの基礎そのものです。
次に「中道」の思想について、文献(2)P458,459で記述されている釈尊が修行者に説いたという主旨を次に示します。
『汝の琴の弦が、張りすぎていてもいけないし、緩やかすぎてもいないで、平等な(釣り合いがとれた)度合いを保っているならば、そのとき琴は音声にこころよく、妙なるひびきを発するであろう』
どちらか一方に偏る(行き過ぎる)ことはよくなく、その中間がよいという中の思想と、その中間の領域で釣り合い(バランス)がとれているという調和の思想なのです。これは現代の「ネガティブ・フィードバック」の基本的な考え方そのものです。
ここで、現代の「自己制御理論」の基礎となるのは、ノバート(ノーバート)・ウィーナーが1948年に著作した「サイバネティックス」という思想であり、具体的にはこの思想の中核となる「フィードバック制御」理論のことです。
これに関して、このHPの「仏教思想と自己相似集合」という見出しのテーマのシリーズで、「サイバネティックス」と「ネガティブ・フィードバック」というテーマで詳細に考察しています。これらをぜひ参照してください。
人間を構成する五薀(ごおん)は、「サイバネティックス」の原点
日本で最もよく知られているお経は、大乗仏教の「般若心経」なのですが、約20年前、仏教を知らなく全く興味がなかった私に、興味のきっかけを与えたのが、このお経の最初の文章でした。
「人間を構成する「五薀」を、すべて「空」と見極めることで一切の苦から解き放たれる」という文章です。なぜ興味のきっかけになったかは、これから考察します。
ところで、文系では、人間の精神(心)を唯一の拠(よりどころ)と考えている人は多いのではないでしょうか。このため人間と人間が作った機械とを同一として扱ったら、「とんでもない」とお叱りを受けるかもしれません。
一般に、人間の心は美しいとか、人間の心は無限の可能性を秘めていると、よくいわれています。
たしかに、神が人間を創ったのなら、これらの言葉は納得できるのです。「この世の一切は縁起で生起する」という仏教においては、人間の心を特別扱いはしないのです。むしろ人間の心は煩悩を生みだす原因として、「空」とか「無」にすることを要求されるのです。
それでは縁起によって生みだされた人間を、仏教ではどのように表現しているのでしょうか。
人間を構成する要素として、「五薀」と呼ばれる五つの要素で表現しているのです。これは原始仏教でも、『これら五つの構成要素が自身であると世尊は説かれた。』(文献(2)p235)と記されています。
これは、「(1)物質的なかたち(色)、(2)感受作用(受)、(3)表象作用(想)、(4)形成作用(行)、(5)識別作用(識)の五種であり、これらの五種のはたらきの交錯において個人存在が成立していると考えたのである。」(文献(2)p159)と記しています。
すなわち、五つの機能が組み合わされて人間の存在が成り立っているとしています。現代では、何らかの仕組み(システム)を容易に理解するために、仕組みの構成要素に着目して、それらの情報の流れをブロック・ダイアグラムで表現するのが普通なのですが、このような考え方を先取りしているのです。
「五薀」をブロック・ダイアグラムで表現すると、下図(図1)のようになります。
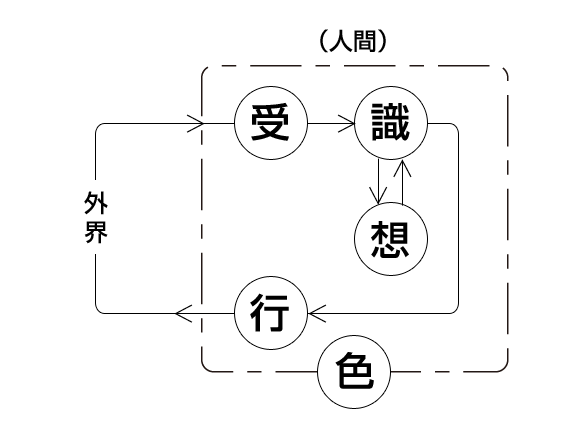
図1.人間の構成要素としての「五薀」のブロック・ダイアグラム
ここで、(1)色は人間の肉体を意味し、(2)受は人間の感覚器官です。(3)想は、感受したものを表象する作用で、意識に現れる外的対象の像、すなわちイメージを心に思い浮かべる作用です。一般には、対象が現前しているときの知覚表象、記憶によって再生される記憶表象、想像による想像表象があります。(4)行は、形成するもの、あるいは形成されるものの意で、人間の行為(出力)機能であり、口や手足に相当するものでしょう。(5)識は、人間の意識の機能であり、認識し、思考する心のはたらきです。脳に相当するものです。
このブロック・ダイアグラムを見て、気がつくことは次の二つです。
(1)人間が作った機械、ここで考察した自己(自動)制御理論によって作られた機械(システム)によく似ていると思いませんか。(「ネガティブ・フィードバック」参照)
(2)アメリカの数学者N.ウィナーによって提唱された「サイバネティックス」」という一つの学問分野です。(「サイバネティックス」参照)
この(1)と(2)に関する著書の副題は「動物と機械における通信と制御」というものです。
ここであらためて図1を見ると、これは人間の周囲の外界を含めて、各構成要素の機能が情報の伝達(通信)をすることによって、何らかの制御がなされる仕組み(システム)です。
すなわちN.ウィナーは、人間であれ、他の動物であれ、そして人間が作った機械であれ、「通信と制御」という切り口から観察したならば、同一の土俵で研究することが可能であることを学問的に明らかにしたのです。
これは文系と理系の融合が可能であることを学問的に証明したとも解釈できるのです。
原始仏教では、後に「唯識」思想としてさらに発展するのですが、人間をN.ウィナーが指摘した「通信と制御」の視点から捉えていたということです。これも驚嘆に値することなのです。
N.ウィナーは、現代の情報化社会の到来を予想した代表的な一人なのです。現在は情報化社会の真っただ中にあり、社会での一切の生活、つまり娯楽、教育や、農林水産を含めた一切の企業活動において、「通信と制御」という「縁」で運用がなされているのです。
すなわち現在こそ、文系と理系が融合しないと成立しない社会であることを、誰もが認識してほしいのです。そして、「原始仏教」や「サイバネティックス」の思想が、もっと評価されて然るべきなのです。
縁起から生起する「空」の境地
仏教最大の難問、仏教でいう「空」は、縁起で生起可能なのでしょうか。文献(3)p139,140で、次のように記されています。
「最初期の仏教の発展のある時期において、認識作用は究極の原理と見なされていた。『いかなる苦しみが生ずるのであろうとも、すべて認識作用によって起こるのである。認識作用が消滅するならば、苦しみが生ずるということは有り得ない。』
「認識作用が消滅する」というのは、何を意味するか、現代人にはなかなか解り難いが、恐らく禅定に入って認識作用が停止し、したがって認識作用のなくなった状態を考えていたのであろう。
・・・
「認識作用」として叙述されているものは、「空」の境地を思わせるものであるが、「空」の境地が認識作用(識)であるということは、後世の唯識哲学の基本的な思想である。」
「空」とは、「一切が存在しない空っぽ」という意味ではなく、認識作用が停止した結果「一切の存在を分別(分節)できなくなった状態」すなわち「一切の存在の区別のできない混沌とした状態」と解釈できるのです。つまりこの状態で新たな視点で分別(分節)することが可能ならば、新たな何かが生まれる可能性があるということです。
すなわち「空」は、一見空っぽのように見えますが、「この世の一切を縁起で生起する可能性を潜在している状態」と見極めることができるのです。これを現代風に解釈したのが、見出しのテーマでの「「無」から「有」を生み出す東洋思想」のシリーズの「「無分別の分別」の現代版 、iPS細胞」です。
それではこの「一切の存在がいまだ分別(分節)されていない混沌とした状態」を縁起によって如何に生起させることができるのでしょう。これは現代の数学のカオス理論が解決してくれます。
このHPの初期の頃、見出しテーマ「華厳経の風景」の一連のシリーズで扱って考察している「縁起の連鎖」すなわち「漸化式」や「決定論的カオス」という用語がこれに相当するものです。
縁起や縁起の連鎖は、因縁によって必然的に結果が決まってしまう、いわば決定論なのですが、現代になって学問的に、このような因果関係から、サイコロを転がしたときの結果のように、全く予想不可能な状態を生起させることが可能であると証明されたのです。これを「決定論的カオス」といいます。
今回展示した画像は、数学という言語を基に、電脳の認識作用の能力を借りて、決定論的カオスに近い状態をいろいろな切り口で分節することを試みて、生み出したものです。
つまり、人間であれ電脳であれ、認識作用には、美しい何かを生み出す無限の可能性が潜在するということなのでしょう。
(1) 仲田 紀夫「タージ・マハールで数学しよう」(株)黎明書房1987年6月
(2) 中村 元 「原始仏教の思想 上 」(株)春秋社、昭和45年9月
(3) 中村 元 「原始仏教の思想 下 」(株)春秋社、昭和46年9月