仏教でよく用いられる比喩と数学的センス
今回は前回の続きです。
前回考察したように、数学とは、現実の世界で細分化された無数の具象や現象を、可能な限り分割以前の状態に戻してから、それらの関係性を数式として定式化し表現することなのです。
ここでいう細分化された無数の具象や現象を、可能な限り分割以前の状態に戻す作業とは、抽象化という手法を用いるのですが、これはそれぞれの共通点のみを抽出するもので、物事の区別・差別を無くする方向に作用し、普遍化・一般化を意味します。そしてこの抽出した共通する事柄の仕組みや構造を詳細に調べ、その関係性を定式化するのです。
このように、数学とは、この世の中での、適用範囲のより広い普遍的な関係性を、誰でもが容易に理解でき、思考や新たな創造のために利用することを可能にすることなのです。
ただし、抽象化の度合いが極めて高い状態の関係式は、私を含め一般の人には全く理解できないような場合が多々あるのですが、これとても専門的に勉強しさえすれば可能なのです。
今回は、この高度に抽象化された状態とは、何を意味するのかということと、これと仏教の「悟り」や「空」の境地との関連について考察します。
仏教でよく用いられる比喩の重要性
ここでは、前回引用した鈴木大拙の文献「仏教哲学における理性と直観」で考察を続けます。前回引用した部分のすぐ上の部分を引用します。
『仏教ではこの般若直観の本質をよく月と水に譬えている。月が多種多様変化極まりない水に映る。それは雨の雫から大洋の限りしれぬ広さに至るまで、あますところなく、月がその姿を水に映して、如何なる変化にもその純一な清浄さを保っている如くであるという。』
この世の一切の存在を、静的に捉えるとしたら、その形に着目することになるのですが、この形は無数に存在するのです。たとえば、一枚の鏡でも、滅茶苦茶に砕いたら、無数の形になるのです。この場合、どのような形のものでも鏡であることは、誰でも直観ですぐにわかるのです。なぜでしょう。
それは、反射するという機能に着目しているからなのです。すなわち、分割する前の元の状態に戻すには、機能に着目して、同じ機能のものを拾い集めて一括すればよいのです。これは同じ機能のものを抽出することであり、抽象化を意味するのです。
上記引用文では、月が水に映し出される機能に着目し、水が多種多様に変化した形状でもその機能(関数とか縁起)は同一であると察知することが、般若直観の本質の如くであると言っているのです。
この文献には多くの禅問答が引用されているのですが、その一つ(p131)に,
問、「古鏡未だ磨かれない時如何。」
師、「古鏡。」
問、「磨かれた後如何。」
師、「古鏡。」
この「古鏡」とは、分化以前の自己の別名と言ってよい。「磨く」とは、分化するということ。「古鏡」は分化するとせざるとに拘わらず依然として古鏡である。』
これも写りの善し悪しは別にして、機能に着目していることは明らかなのです。
このように、抽象化をするにあたって、数多くの事物の中からその共通点を見出すとき、その機能に着目するということは、いままでも考察をしていますが数学において、きわめて重要な項目の一つであり、これが関数として表現されるのです。
ただし、先にも記したように、高度に抽象化された機能になると、凡人には理解できなくなり、あるいはカオスが生起するような状態では電脳の助けを借りないと理解できないことになり、このような領域では「理性」より「直観」が重視されるのです。
なお、「般若直観」の「般若」とは、広辞苑によると、「真理を認識し、悟りを開くはたらき。最高の智慧。」のことです。
「般若直観」・「空」の「場」の作用
鈴木大拙のすごいところは、「悟り」に関して、その事態をきわめて詳細に記述し、考察していることであり、かつこの説明に合理性があり、現代人が十分納得できることなのです。古代の仏典のみを唯一の拠にしている仏教学者ではないのです。
同じ引用文献のp150に、次のように記されています。
『般若直観に作用された般若の場というものは、時として未分化(無差別)の場として、又或る時は差別の面にはたらく場として取り上げられるものだが、この差別の作用というものが、この場以外のものから加えられたはたらきであると考えてはならない。差別の作用は、この場そのものの内部から発展するものである。
何故かというと、般若の場というべきものの本質は、決して、空の情態、即ち絶対の無作の姿で、いつまでも、じっとしているようなものではないからだ。
般若の場のほんとうの姿は、自分自身を無限に差別し分化することを要すると同時に、どこまでも未分化・無差別のままの情態にいようとするものだ。
・・・・・・
自己自身を分化せしめ、しかも同時に未分化の情態にありつつ永遠に創造の作用を続けていくもの--これが空である。これが般若の場なのである。』
みなさまはこのアンダーラインの文章を理解できますか。文章上に難解な部分はないのですが、背反的に作用する「般若の場」の仕組みが、具体的にイメージできないのです。
しかしながら、数学的なセンスがあり、抽象化の作用をイメージできる方なら理解できるのでしょう。
そこで抽象化の作用を、誰でもがイメージできるよう、目で見える「機械的」な構造として説明します。
抽象化のイメージを表す木構造と自己相似集合図形
抽象化とは、複数の事象をその共通点に着目して一つの概念で表すことです。思考や調査によって、この抽象化の度合いを徐々に高めていく過程は、下図(図1)のように木構造で表現できます。
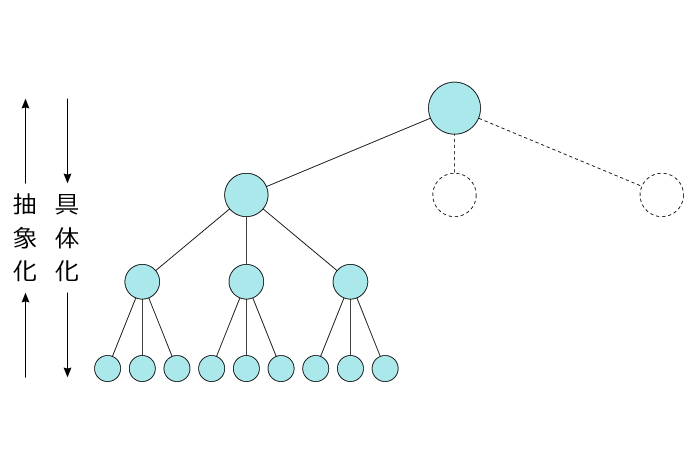
図1.抽象化(統合)と具体化(分割)を表現する木構造
普通、抽象化とは、多くの事象を一括する統合や未分化の状態に戻すことを意味するのですけれども、図1のように目で見える機械的な関係図として表現すると、この図は、自分自身を無限に差別し分化していく過程とも見ることができるのです。
すなわち、分割した以前の事象に戻す作用と、事象を分割する作用とは一体不離なのです。鈴木大拙も引用文献のp106に次のように記しています。
『そもそもいろいろなものを区別し識別する分化作用というものは、何物かがあってそれが集成乃至統合するというはたらきをしなければ、分化作用は不可能なものであるということが納得されると、ここで分化作用をする分別識の根底には般若が在るということ、又、分別識の機能をして分化の原理としてはたらかしめているものが即ち般若であるということは、割合容易にわかるものだ。』
この事態をより明確に表現したのが、自己相似集合図形なのです。実は、木構造も自己相似集合図形であり、木構造の描き方を少し工夫して表現すれば、自己相似集合図形として表現できるのです。
木構造において、一般に円に相当する部分を「節」と呼び、上方の円(節)と下方の円(節)を結ぶ線を、「枝」と呼びます。
図1の木構造の例は、枝の数が三つある3分木構造なのですが、これは三角形の自己相似集合図形に対応するのです。この図については、既に「仏教思想と自己相似集合」シリーズの「木と森の関係」で考察されています。
枝の数が四つある4分木構造は、四角形の自己相似集合図形に相当するもので、「「無」から「有」を生み出す東洋思想」シリーズの「仏教の「悟り」の後に現成する「存在構造」は自己相似集合(Ⅰ)」で考察しています。
これらは、個(木)と全体(森)との関係や、悟りの境地に達した人は、個々の事物をその全体との関係として捉える智慧を得るということについての記述で、これらは自己相似集合図形で表現できるのです。
そして、この自己相似集合図形は、言語的に背反として表現される、統合作用(包括)と分別作用(分離)は、一体不離の関係にあることをも表現しているのです。
抽象化と比喩
だいぶ前の考察ですが、写真を撮るときのズーム・アップ(対象に近づく)とズーム・アウト(対象から遠ざかる)を話題にしたことがありました。
仏教思想で「自己の究明」とは、自己そのものに限定して焦点をあてるズーム・アップで撮影(究明)するのではなく、自己の周辺の環境と自己との関わりを撮影(究明)するズーム・アウトのスタンスが好ましいということです。
対象から遠ざかるとは、まさに抽象化の度合いを高めるということに相当し、自己に対して周辺の環境をより広範囲に拡大し、自己との関連を見ることです。つまり、自己を自然の領域で捉え、自然の一員としての自己のあり方を究明することを意味します。
具体的に、抽象化の度合いを高めるとは、桜の木を、被子植物-植物-生物-自然、と順次範囲を拡大して捉えるということなのです。
すなわち、抽象化の度合いが高い事柄とは、事の内容の意味が広範囲になるということであり、要するに、言語で明確に定義することが難しくなることを意味します。
例えば、誰でもが十分に知っている「自然」とか「植物」を言葉で簡明に定義するとしたら、何と表現するのでしょう。
結局、多くの具体的なものを例に挙げて、これらとの関係性を階層的に(木構造として)説明する以外に方法がないのです。
たとえば、「自然」の場合には、具体的な天空・海・山川・草木などの集合体として説明することになるのです。
以上のように、抽象化の度合いが高い事柄の説明には、これと類似した具体的なものを借りて表現する「比喩」を用いることになるのです。すなわち「~のようなもの」、「~の如し」で一切が表現されるのです。
これはまさに仏教でよく用いられる「~如何」、「~の如し」の世界、すなわち「真如」、「如如」の境地を導くための禅問答の世界なのです。